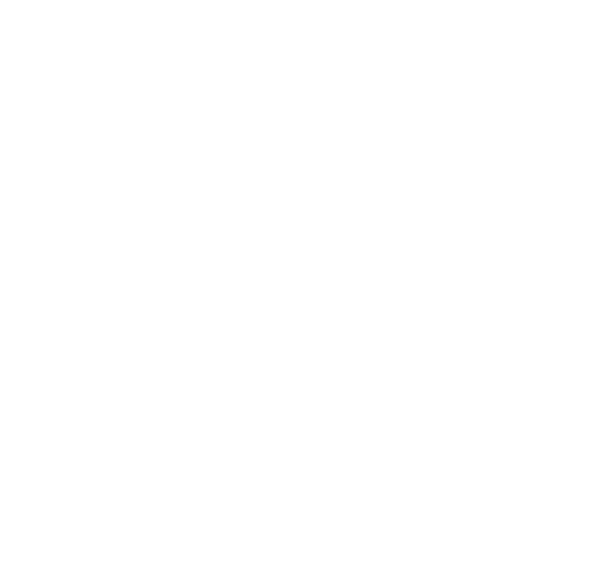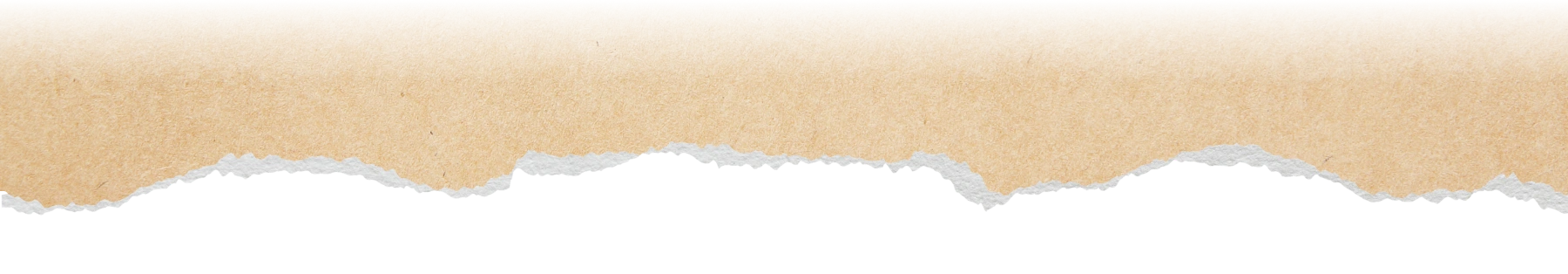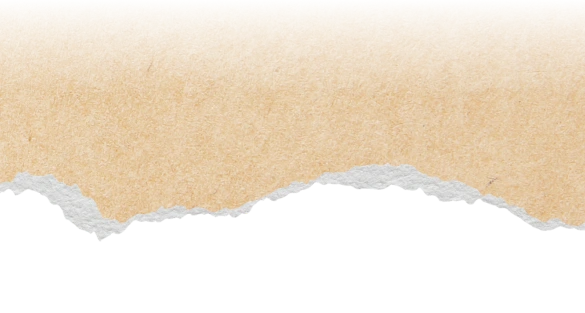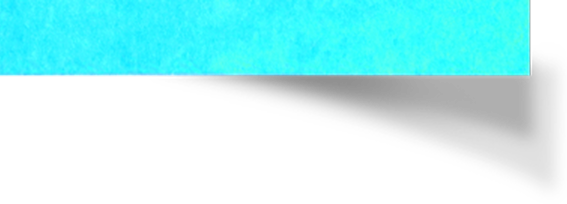






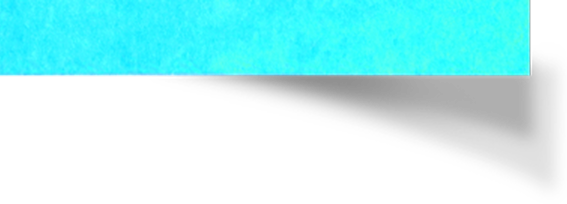
思いがけない出会いとBIOTAの世界
元々BIOTAさんをもっと知りたいと思っていたのとさやかさんからのお誘い、という理由だけで何のイベントなのかも分からず参加したのですが
行ってみたら人が何人かいて、お互い誰なのかも紹介し合わず、アットホームな雰囲気でするっとBIOTAさんの発表が始まりました。すでに面白い。
ずっと微生物の研究をされていたBIOTA代表の伊藤さん、「都市においてどう微生物と触れ合うかを考えた時に、人間の腸にとってのヨーグルト≒都市にとってのランドスケープ!だ」と思いつきBIOTAを創業したそう。とても面白い。
 剪定と菌糸から学ぶ「動的ランドスケープ」
剪定と菌糸から学ぶ「動的ランドスケープ」
今回のイベントは、どうやらBIOTAさんが植栽を担当したwatageのスペースをみんなで剪定&この1年の動きを振り返る会でした。上の写真は、菌糸ワークショップで設置したBIOTAさんの菌糸ブロック。自然に分解されて形が変わっていました。分解された菌糸ブロックは土壌改善につながるそうです。

室内に置いてあったこちらの菌糸ブロックには謎のきのこが生えていたとのこと。
菌糸ワークショップをきっかけにハマった人は自前の3Dプリンターでオリジナルの型を作って楽しむ人までいたそうです。なかなか奥深そう、菌糸ブロック。
 人・植物・微生物が交わる地域の営み
人・植物・微生物が交わる地域の営み
剪定を教えてくださったのはBIOTAのこちらもいとうさん。
いとうさん流の剪定をする理由は
①メンテナンス
②虫に食われる、黒くなるなど植物が自己判断して起こす現象が起きる前に、先んじて予測をして剪定する
管理ではなくいかに愛着を持って、植物と人との関係性を保っていけるかが重要とのこと。
watageの植栽では、新しい生き物が入ってくる容量を空けておくことや、植物たちの強弱をつけて密接に植えることであえて動きを作る動的ランドスケープの形成を狙ったそう。
実際に、ネズミがやってくることが増えて、この日も、昨日寝ていたのかネズミが掘ったであろう穴が形成されていました。
植物たちは、学名で分類して遺伝的系統が全く異なるものを混ぜて、系統的な多様性を保つことで全体の機能性の向上を狙っているそう。そういった環境にしておくと、意図せずにどこかからやってきた他の種が生えてきてしまうこともあるそうですが、それも受け入れるようにしているそうです。素敵です。

剪定して取れた植物たちがこちら。月1の介入でこの量が取れます。
「剪定」をメンテナンス担当・剪定士たちだけが行うものなのか、を考え直したいと言いながら、ずっと植物と対話しながら剪定を進めていくいとうさんと、テーブルを囲んで人と対話を続ける伊藤さん。素敵なITOさんコンビです。
人と人、人と植物、植物と植物、そしてそれらをつなぐ微生物。
色々な関係性を自由に交わらせ、対話を重ねながら”良い場所”を作っていこうとする。
そんな営みが地域で育まれている場所がwatageなのかな、と感じたイベントでした。

帰り道メトロに置いてあった紙袋。
Wet 水がぬれています。申し訳ありません。 と手書きで人形焼の袋に書いて置いてあって下町情緒を感じました。
(Text: Minami Shinohara)