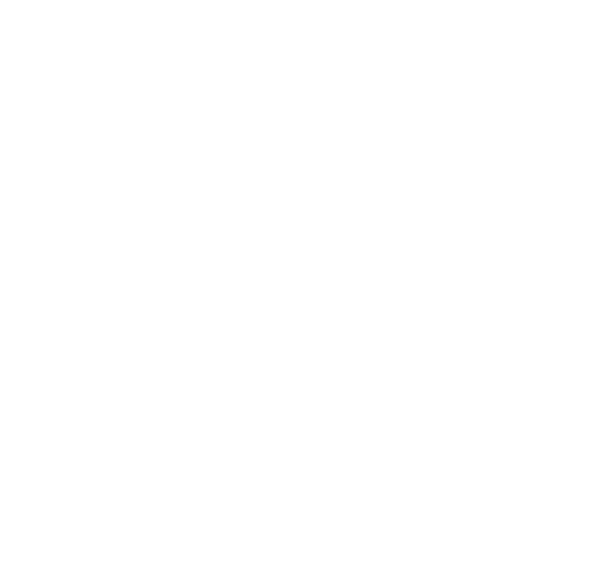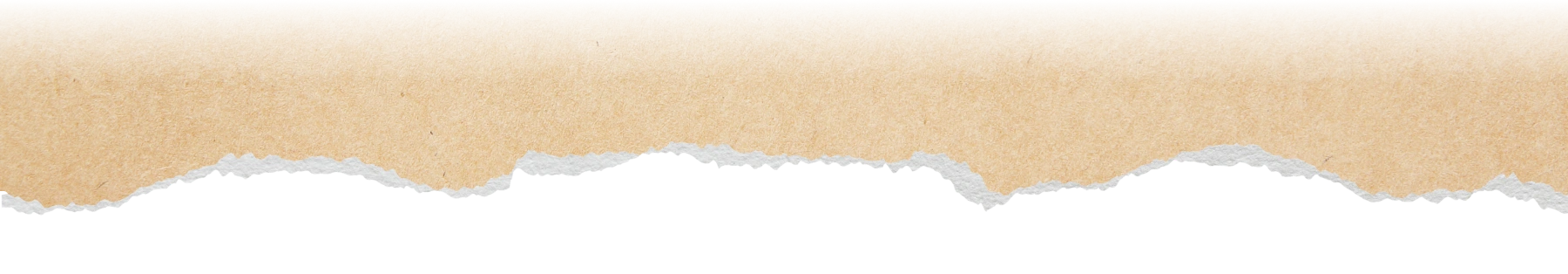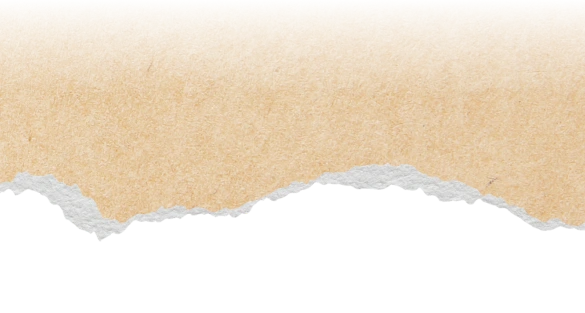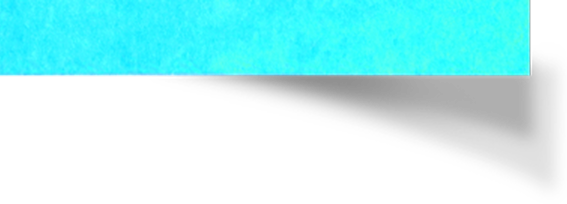
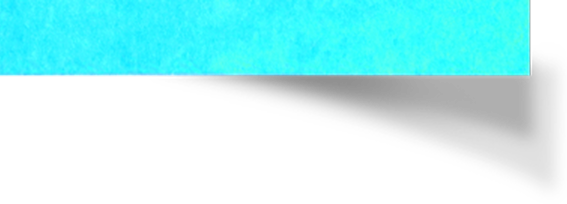
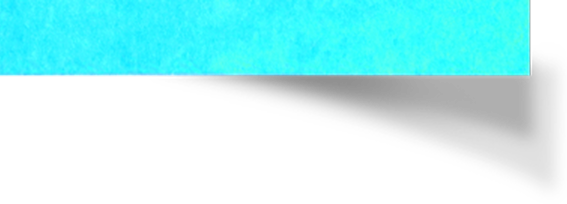



備考:参加カンファレンス
リオ個人@2023
- IVS@京都(スタートアップ企業・WEB3)
- ACK@京都(現代アート)
- GRF@ジュネーブ(難民)
弊社メンバー@ここ数年
- COP26, COP27@グラスゴー、カイロ(環境問題)
- SXSW@オースティン(アート・エンタメ・テクノロジー)
①RE:CONNECTに直接つながる有識者の意見
インパクトハブにてサイドイベント4~5つほど参加して、印象に残ったものをピックアップ。RE:CONNECTに直接つながるフィードバックが意見として提示されていたので、共有。
『RLOとして一番感じている課題は継続的なドネーション・資金巡り。一過性の寄付や支援をいただくことは結構できているが、継続に繋がらない。』
⇨これに関しては、世界中にある全ての課題に置いてほぼ全てのNPO・NGOが感じている事実なので、特に目新しいものではなかったが、何回か違う人から声に上がっていたので単純に物理的に多かった意見として共有。RE:CONNECTをはじめとした、RE:ACTION全体の目標がこの「継続アクションの設計」にあるので、改めてその重要性を認識。
『この業界で20年ファンドレイジングしているものだが、一番言いたいことは、コンソーシアムという概念を全ての解決策として考えちゃダメ。すごくしっかりした根幹がなければ企業は集まらないし、仮に一回集まったとしても、根幹がぐらついていると、その一期だけで終わって継続には繋がらない。』
⇨これは正直かなり耳に痛い意見だった。同時にすごく勉強にもなった。RE:ACTIONのスライドにも、RE:CONNECTも含め「全ての課題や議題でどんどんコンソーシアムを作っていく」が記載されているぐらいなので、褌を締め直さなくちゃ、という気持ちになった。同時に、SEAMESとして関わっている他のコンソーシアムがなんであんなに微妙なのか(あまり具体名はあげたくないが、渋谷のFDSなど)が腑に落ちた。
『私が課題だと感じるのは、こうやって集まっている一週間はみんな色々と盛り上がって「ぜひコラボレーションしよう」と話になるが、いざそれぞれ母国に帰るとまるで何もなかったかのよう日常に戻って、ほとんど実現されない。』
⇨これはGRFに限らず多くのカンファレンスの課題ではあると思うが、同時に現実的に短期間で意気投合して実際にプロジェクトをスタートする、みたいなことはそもそも実現数に限界があるとも思っている。ただ、「繋がりを継続させる」という意味合いもRE:CONNECTにはるので、作り方次第では一つの解決策になるのでは。
『RLOとして感じている課題は、結局資金がトリクルダウンしてこないこと。トリクルダウンしたとしてもごくわずか。ほとんどの企業は緊急支援として国際NGOにお金を寄付するけど、緊急じゃなくなったRLOには回ってこない。また国際NGOを経由してくる資金も自分達に届く頃にはほんのわずかの金額になっている。』
⇨これはナジーバさんの言葉だったがすごく刺さった。後にも書くが、全体的にこの「インパクトハブ vs パレクスポ」の対比が「RLO vs 巨大機関」すなわち「継続支援 vs 緊急支援」になっていて、ナジーバさんの悲痛さが伝わってきた。同時に、これもRE:CONNECTが対策しようとしている明確な部分なので、改めてRE:CONNECTのポテンシャルを感じる言葉だとは思った。
②GRFに関して
前提として、12日(WJとともに行動)13日(インパクトハブ)14日(パレクスポ)15日(午前はプレゼン@インパクトハブ)で行動しており、GRFに関しては14日の体験と、それと比較したインパクトハブ+他のジュネーブでの体験となっている。また、分類としては体験としてハードとソフトに分けている。
ハード
全体的な雰囲気の暗さ・重さ
ベニュー
パレクスポ自体が「冷戦時代に作られたのか?」と思わせるほど全体的に雰囲気が暗く、ベニューの素材が重めの石やコンクリートと、それに合わせて照明も若干暗かった。
全てが青い
これは国連系のイベントだから当然なのかもしれないが、至る所が青かった。「青しか色を知らないのか?」ってレベルで全てが青い。もちろん、「これは国連関連のイベントだよ」という意味でのオフィシャル感を出すのにはすごく有効で、広報用の素材を撮ったり、家族や友達に写真で「おお、すごい!」と思わせる場合とかにはいいのだが、青色というのはそもそも心理的にはDepressantカラーであり、ずっと青に囲まれていると気が滅入ることは化学的に証明されている。それに加え地味に暗いコンベンションセンター、テーマはそもそも軽いものではない難民問題と、全体的にどんよりする空気に加担していた。
以下のように、青じゃない色が使われている見せ物があるとそれだけで強く印象に残った。
インスタレーションの曖昧さ
上記のa.b.に対するせめてものも対抗手段としてインスターレーションをいくつか設けていたと思うのだが(観葉植物も微妙にあった)、どれも正直パッとしなかった。一応各インスタレーションの隣に立っているスタッフに全員話して見たが、半分ぐらいが「うーん、僕もこれなんだかよくわかってないんだよね、あはは」みたいなリアクションをされた。唯一パッションを持って語ってくれたのは難民が作ったグッズの物販だった。ここの人たちとの交流のみが@パレクスポで少し気持ちが上がった瞬間だった。
なお、比較対象として国際赤十字博物館に行って見たが、世界中で色々な展示を見てきた中でも、「災害・人災に置いて被害にあった人」に対して心の距離を詰める演出はトップレベルだった。
上:難民のかたと一回画面上で物理的に手を合わせないと話し始めない演出。
下:「難民であることはずっと鎖で縛られているような気持ちだ」という言葉をインスタレーションで表現。実際に天井から吊るされた無数の鎖を通らないと進むことができず、来場者が物理的に重さや痛みを感じる使用となっている。
役割の違いはわかるけど…
もちろん、GRFの主目的は啓蒙活動じゃない、ということはわかっている。そもそも各国・企業・財団などのプレッジがなされる場所で、同時にGRFにきている人間な時点で一定レベルでこの課題についての理解や関心があり、ほとんどの人間は具体的なアクションをとっているはずなので、このフォーラムに置いて一般大衆に向けた0→1を生む必要がないのはわかる。それでも、本当に「世界の力を合わせて変化を起こそう」というのが根底にあるのだとしたら、もう少し全体的にポジティブエネルギーた必要だと思った。(逆にいうとインパクトハブではこれを強く感じた)

ソフト
Under-Representation
こちらはGRFメッセンジャーグループでも少し書いたが、正直これは本当に「Global」Refugee Forumなのかなと?本当は「Mainly African and Middle Eastern, and slight South Asian and South East Asian」Refugee Forum 「Supported by Wealthy Western Nations」じゃないのかと…。
上記は皮肉で書いているが、実際のところ東アジア人はほとんど見かけず、たまに遭遇しても津田先生であったらたむけんさんだったりした。僕がパレクスポにいたのが二日目で、外務省周りの人間がすでにいなかったからだとも思うが、自分以外の日本人は1グループしか遭遇しなかった。なお、韓国人もWJのシンポジウムに参加した二人しか見かけなかった。これはかなり衝撃で、他のグローバルカンファレンスではかなり世界的にもあらゆる各国からの人間を見かけるのでそれを想定して行ったのだが、このままだとそもそもRE:CONNECTを日本スタートにするべきなのか、β版から多少は同時多発に進めるべきなのか、と真剣に考えさせられた。
同時にさらに衝撃だったのは中米・南米の人の少なさだった。こちらに関してはベネズエラの難民問題、ギャング抗争や貧困を抜けようとメキシコを通ってアメリカの国境で捕まっている中米各国からの家族問題(そして親と子を引き離すアメリカの国境警備問題)など、ドセンターなはずなのにここまでいないのはなぜなのか?と心底理解できなかった。
メディアプレゼンス
こちらも衝撃的だったのだが、メディアプレゼンスのあまりにも少なさ。自分は普段、主要ニュースとしてはNew York Times, The Atlantic, The New Yorkerの三つのニュースレターが普段届くのだが、GRFについての言及はほぼ皆無。例えばNYTのニュースレターは構造上「 A. その日の主張ニュース(結構ガッツリと記述されいてる)」「B. その他主要ニュース(1パラグラフぐらい書かれている、一日に4~5トピック)」そして 「C. その他一応記載ニュース(文章一つ 10トピックほど)」となっており、GRFの開幕はCにすらなっていなかった。あまりにも信じられず、数日前後のニュースレターも確認したが、やっぱりなかった。対してGRF開幕直前まで開催されていたCOP28は連日Bで取り上げられ、サウジの石油離れ発言が出た日に関してはAまで上がってたので、この違いはあまり悲しかった。
同時に、それはパレクスポでも見てとられ、メディアルームは階段を登った奥の押し入れみたいなところにあり、普通に間違って入って見回したら”MEDIA” って書いてあり、「え、ここがメディアルームなの?ちっさ!」って思ったのを覚えている。
このメディアの不関心さ?なのか?は正直どこかどうしたらなんでこうなったのか全くわからないのだが、ある意味一番解決すべき部分かもしれないと感じた。特に各国メディアが連日連夜イスラエル・ハマスを取り上げている最中だったのでなおさら…多くの人が認知して責任を取らせるから意味をなすプレッジではないのか??
やっぱり暗い
これは上記のハードの部分とも連動しているので短く済ませるが、全体的に厳格なムードのせいで、盛り上げようとする少数までも気落ちさせられてる感じがして悲しかった。
具体的な例で言うと、Artolutionのメンバーがパレクスポで話した時も、おそらく普段やるようなピッチで軽快に楽しく話していたのに周囲は完全に「ちーん」だった。また、メンタルヘルスの会の最中も、来場者のことをことを考えて「我々のメンタルヘルスも大事だよ!ちょっとこの時間使って深呼吸しましょう」とか発言されても、周囲は総じて「そうね…はは(苦笑)」みたいな雰囲気で、正直いたたまれなかった。
総評
途中でも書いたが、GRFは国連関連のイベントであり、世界各国の政府から要人がきている時点で厳格さ・重厚さが必要なのは理解している。なので、「これってハックできるんじゃないか?」みたいなことは基本的には考えていない。ただ、逆に、GRFが文字通り「青」だとすると、同じテーマで、全く正反対の見せ方(例えばテーマカラーが「蛍光色」とか「パステルピンク&グリーン」とか)のものが絶対的に必要なのも感じた。そのエネルギーはインパクトハブで感じたので、あとはどうやってもっと一般の人に伝わっていくか、かなと。(もちろん世界難民の日の渋谷駅での取り組みとかもあり、我々も参加していたのでわかるが、今振り返ってみるとあれでもまだ弱い、と気付かされた)
また、お世辞とかではなく、間違いなくWJのシンポジウムは今回のジュネーブでのハイライトのひとつだった(最終日にサウナに入ったあと湖に飛び込んで、隣で泳ぐ白鳥と一緒に素っ裸で水面からリッツカールトンを見上げたのと同率1位です!笑)。日本という、GRFにおいて目に見えるレベルでアンダーレペゼン状態の国でいかに「難民問題」について考えるか、そしてアクションしていくかに対する素晴らしい解答(そしてemPATHyはまじで希望!)になっていると感じ、関わって準備されたWJの皆さんには「本当にお疲れ様でした!」と「本当にありがとうございました!」伝えたいです。
最後に、RE:CONNECTは来年前期にPhase2であるβ版の完成を目指しており、そこからのPhase3からローンチまでは相当大きなお金・人・アイデアが動くプロジェクトなります。①-2の女性も述べていましたが、企業・団体・機関・個人が集まる根幹の部分はこちらでしっかりとガチガチに固めていきますので、どうぞ少しでもお力添えをお願いできればと思います。また同時に、僕が力になれそうなことがありましたらいつでも連絡ください。どうぞ引き続きよろしくお願いします。
(Text: Leo Kominz)